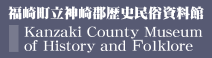わら〜わらのある暮らし〜
平成15年10月25日〜11月24日
今回の特別展は、生活のあらゆる場面に利用されてきた藁製品や道具などを、資料館に収蔵されている資料を中心にご紹介しました。
神崎郡では、明治37・38年ごろ日露戦争の軍用叺(かます)の供出により藁製品である莚・叺(むしろ・かます)の生産は飛躍的に発展し、大正末頃には副業として郡産業の中心となりました。
しかし、昭和30年ごろからの高度経済成長の中で、プラスチック製品やビニール製品におされ、長年用いられてきた用具や伝承技術は姿を消しつつあります。
一方、現在にも残る民俗行事においては藁はあまり姿を変えずに用いられています。鍛冶屋地区のかくしほちょじ、高橋地区の法成就講、また虫送りの時に使われる藁で作られたサネモリ人形など、これら民俗行事と藁との関わりについてもご紹介しました。
会期中には多くの方にご来館いただきました。展示を通し、今日の暮らしを再認識し、先人たちの知恵と工夫を見直す機会となっていただけたのではないでしょうか。
|
 |
● Web展示室 |
 |
 |
 |
| 叺(かます) |
タテ |
 |
 |
 |
| 飯櫃・飯櫃ふご |
藁草履 |
 |
|
|