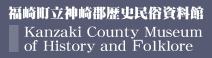|
平成23年度 神崎郡歴史民俗資料館講座開設のお知らせ |
|
● 歴史民俗資料館連続講座のご案内
 平成23年度連続講座のご案内 平成23年度連続講座のご案内
平成23年度も、歴史民俗資料館で郷土の歴史や民俗行事について
学ぶ連続講座を全5回を行いました。
本年は、「地域の歴史文化遺産は郷土のたから」をテーマし、新たに古文書講座も開催しました。
本講座をとおして地域の歴史を知り、そして当時の史料を読み解く時間をお楽しみいただけたでしょうか。
ぜひまた来年度もお気軽にご参加ください。
「地域の歴史文化遺産は郷土のたから」
~郷土への誘い~
 各講座の紹介 各講座の紹介
| 開 催 日 |
講 座 名 |
講 師 |
場 所 |
時 間 |
| 第1回 |
5月21日(土) |
古文書からみる福崎
~郷土の歴史資料を読み解く魅力~ 済
|
河野未央氏
(神戸大学
地域連携センター) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第2回 |
7月9日(土) |
柳田國男のふるさと~神崎郡の古代の神話~ 済 |
坂江 渉氏
(神戸大学) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第3回 |
9月17日(土) |
化石のはなし
~福崎の古い地層~ 済 |
古谷 裕氏
(県立人と自然の博物館)
|
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第4回 |
11月12日(土) |
三木家と柳田國男 済 |
山﨑善弘氏
(奈良教育大学) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第5回 |
2月18日(土) |
播磨地方における毛獅子の現在 済 |
大渡敏仁氏
(芸術文化学博士) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
 平成23年度講座録集 平成23年度講座録集
<第5回 講座録>
日 時:平成24年2月18日(土) 13時30分~15時
演 題:「播磨地方における毛獅子の現在」
講 師:大渡 敏仁氏(芸術文化学博士)
2月18日、歴史民俗資料館にて、本年度第5回目の連続講座が行われました。
今回は、播磨地方に多く伝わる獅子舞の中から、毛獅子について、
その特徴や伝播についてご紹介いただきました。
しかし、講座では本来別テーマをご用意いただいておりました。
大渡先生の講演では、現地調査をもとに、映像記録や聞き取り、文献等から
考察いただき、それぞれの事例について紹介いただいています。
今回は事前調査時に、祭礼の日時が変更されていたため、現地調査が叶わず、
先生のご専門である、獅子舞にテーマを変えて、ご講演いただきました。
毛獅子のお話では、現在においても多くのところで伝承されていることを知り、
中でも、梯子獅子は播磨特有のものであるということや、毛獅子の伝播経路など、
播磨地方における毛獅子の現状について認識することができました。
今回の講座を通じて、現代において伝承文化を継承していく上での課題や、
播州は祭礼豊かな地域であるということを改めて実感することができました。
これからも、講座では現代に伝わる地域の貴重な民俗芸能を、
ご紹介していきたいと思います。
どうぞ来年度の講座もよろしくお願いいたします。
<第4回 講座録>
日 時:平成23年11月12日(土) 13時30分~15時
演 題:「三木家と柳田國男」
講 師:山﨑 善弘氏(奈良教育大学 特任准教授)
11月12日、歴史民俗資料館にて、本年度第4回目の連続講座が行われました。
今回は、今年福崎町で50年祭が行われた柳田國男について、
國男が幼少期に一時預けられていた三木家との交流について、
現存する書簡などから読み解いていただきました。
三木家は、江戸時代大庄屋を務め、当時の職務の内容については、
山﨑先生自ら、三木家文書の解読を進めていただき、近年少しずつ明らかになっているところです。
講座では、まずこの三木家について詳しくお話いただき、
歴代当主の、学問や文化に対して非常に高い意識を持ち、またそうした才能にも恵まれていた点、
そして、文化人として豊かな交流を築き、地域文化の担い手としての役割を果たしていたことを、
教えていただきました。
そして、近代には、柳田國男がこの三木家で一時期を過ごすこととなります。
そこでは、三木家の蔵書との出会いや、生涯にわたり竹馬の友として親交を深めた、三木拙二との
出会いも大きなものでした。
ちょうど展示室では、特別展を開催しており、本日教えていただいた内容を知ることができる、
資料を展示しています。
本日の講演を通じて、当町において柳田國男、そして三木家という重要な要素が、
ともに大きな位置付けであることを、改めて認識できたのではないかと感じます。
また、こうした現存する地域資料の研究を進めることで、当時の歴史を知り、
そして豊かな文化交流を育む福崎の歴史文化をより深く知ることができるのではないかと、
感じることもできました。
こうした地域資料の魅力を、今後も資料館から発信していきたいと思います!
どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
<第3回 講座録>
日 時:平成23年9月17日(土) 13時30分~15時
演 題:「化石のはなし~福崎の古い地層~」
講 師:古谷 裕氏(兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員)
9月17日、歴史民俗資料館にて、本年度第3回目の連続講座が行われました。
今回は、私たちの住む台地がさまざまな地層から成り立ち、その地層に含まれる
化石について、大変詳しくお話いただきました。
そして化石のなかでも、‘放散虫’について紹介いただきました。
化石とひとくくりに表現してみても、放散虫のような小さな微化石から恐竜のような大型化石まで多様です。
本講座では、先生のご専門である‘放散虫’につい教えていただき、その生態や放散虫と
地層との関係など、放散虫の魅力をたくさん知ることができました。
講座は、講話だけではなく実際の化石を見たり、福崎で確認された話などから、
より身近に感じることができました。
ちょうど展示室では、県立人と自然の博物館との共催展である化石展を開催していました。
展示と合わせて認識を深めるとともに、地質や古生物の世界を知り、
参加されたみなさんも、新たな興味・関心を高めることができたのではないかと感じます。
次回は、今年50年祭が行われた柳田國男が講座で登場します。
展示室では特別展「民俗学のふるさと福崎~幼き國男に刻まれた福崎文化~」
を開催しますので、あわせてお楽しみください。
<第2回 講座録>
日 時:平成23年7月9日(土) 13時30分~15時
演 題:「柳田國男のふるさと~神崎郡の古代の神話~」
講 師:坂江 渉氏(神戸大学大学院人文学研究科 特命准教授)
7月9日、歴史民俗資料館にて、本年度第2回目の連続講座が行われました。
今回は、『播磨国風土記』をとおして、風土記の特色や古代の神崎郡の神話などに
ついて、丁寧に教えていただきました。
風土記からは、私たちの住む郡名や地名に由来する起源を知ることができ、
現在もその地域に伝わる話への理解や親しみを深めることができました。
また、巨人神と小人神が活躍して「国づくり」をする話や、神戦さの話は、
ユーモアに富む表現で記されており、状況を想像すると、より風土記の世界の魅力を
感じることができました。
こうした貴重な地誌が『播磨国風土記』として残り、のちには、郷土の偉人である
柳田國男や兄 井上通泰も研究したテーマでもあります。
風土記とともに、こうした功績を知ることもふるさとを再認識するきっかけと
なるのではないでしょうか。
8月6日(土)、7日(日)は柳田國男50年祭が開催され、さまざまなもよおしがあります。
ぜひみなさんご参加ください。
本日もたくさんの方々にお越しいただきありがとうございました。
次回は、時代の軸がぐっとさかのぼりますが、化石のはなしです。
展示室では兵庫県立人と自然の博物館との共催展
「歴民に化石がやってくる!~第4幕 新生代~」を開催しますので、
あわせてお楽しみください。
<第1回 講座録>
日 時:平成23年5月21日(土) 13時30分~15時
演 題:「古文書からみる福崎~郷土の歴史資料を読み解く魅力~」」
講 師:河野未央氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携んセンター 研究員)
5月21日、歴史民俗資料館にて、本年度第1回目の連続講座がはじまりました。
今年は、「地域の歴史文化遺産は郷土のたから」をテーマに、
郷土資料をとおして、ふるさと再発見をお楽しみいただきます。
第1回目は、郷土の歴史が記録されている古文書史料の魅力について、
くずし字の読み方、内容など一つ一つ丁寧に教えていただきました。
講座では、町内の村史料を参考にご紹介いただき、
当時のようすについても知ることができました。
また、参加者の皆さんにもくずし字読解に挑戦いただき、
‘聞く’だけではなく‘向き合う’ことで、古文書史料の実際を体感いただけたのではないかと思います。
当日皆さんからいただいた声なども参考にさせていただき、
今後は古文書講座開設に向けて準備を進めていきます!
本日はたくさんの方々にお越しいただきありがとうございました。
次回は、『播磨国風土記』などからみる地誌を中心に、当時のようすについてご紹介いただきます。
8月には柳田國男50年祭が開催されます。
私たちの郷土に残る神話をぜひお楽しみください。
 今までの講座録集 今までの講座録集
・平成22年度講座録集
・平成21年度講座録集
・平成20年度講座録集
・平成19年度講座録集
・平成18年度講座録集
・平成17年度講座録集
・平成16年度講座録集
◆問合せ先◆
神崎郡歴史民俗資料館
℡:0790-22-5699
※お問合せ・お申込みは資料館まで。 |
|
 |
|
|