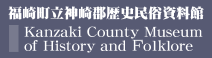● 建物のあゆみ
この建物は、明治19年(1886)、神東・神西郡役所として、神東郡西田原村辻川(いまの福崎町西田原辻川)に建設されたものです。建設費は当時の金額で2,029円14銭で、施工は姫路の中島林平があたりました。明治29年(1896)には神崎郡役所と改称され、大正15年(1926)に廃止されるまで、郡役所として使用されました。
その後は、県の地方出先機関の事務所などに用いられていましたが、老朽化にともない、いったんは取り壊し、跡地売却の方針が決まりました。しかし、地元文化団体などの保存運動のなかで福崎町に譲渡され、昭和57年(1982)3月、国・県および神崎郡内各町の助成を得て、現在地に移築・復元し、10月には福崎町立神崎郡歴史民俗資料館として開館しました。
また、昭和62年(1987)3月、県重要文化財の指定をうけました。 |

▲大正ころの神崎郡役所 |
 |
● 建物のあらまし
木造、寄棟造り、日本瓦葺き、下見板張りのペンキ仕上げ、均整のとれた堂々とした外観の洋風建築です。正面の主屋は二階建で、背面に平屋建がつづき、基礎部分には花崗岩が用いられています。
中央にはりだした玄関部は、ギリシャ建築様式をとりいれた二段式で、一階部は角柱、二階部は円柱とし、円柱の頭部には古代ギリシャのコリント風「アカンサス」の葉が丹念に彫刻されています。
ガラスや階段の手すりは手づくりで変化にとみ、元郡長室には洋式暖炉が設けられています。
この建物は、玄関部をはじめ内外の意匠に多くの特色をもった文化財であるとともに、明治以来、当地方発展の中心的役割をはたした記念的建物でもあります。 |
 |
 |
 |
| ▲階段の手すり |
▲アカンサスの葉の彫刻 |
▲郡長室の暖炉のあと |
|
 |
● 館内案内 |
| 木造2階建 |
延343.42m2 |
| 事務室 |
18.93m2 |
| 収蔵室 |
40.90m2 |
| 展示準備室 |
15.14m2 |
| 展示室 |
99.15m2 |
| 元郡長室 |
16.52m2 |
| 2階多目的学習室 |
98.02m2 |
| ポーチ・バルコニー |
12.54m2 |
| トイレ |
3.36m2 |
| その他 |
38.86m2 |
|
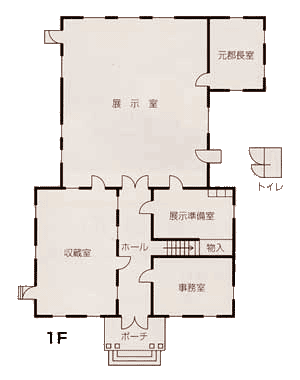
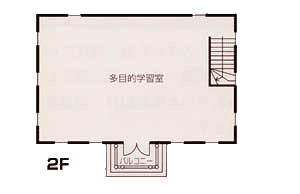 |

▲移築前のようす |
|